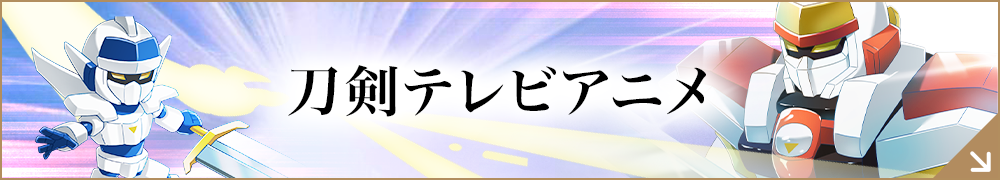刀剣テレビアニメの紹介 - 刀剣ワールド
- 小
- 中
- 大

令和を代表する「刀剣テレビアニメ」と言えば、驚くほどの快進撃を続けている「鬼滅の刃」(きめつのやいば)です。同作品は原作のマンガがテレビアニメ化され、さらには映画化されるなど、「メディアミックス」の手法を採ることで、留まることを知らない人気に拍車をかけています。このようなメディアミックスによる展開は、刀剣テレビアニメにおいて、実は1970年代から始められていたのです。
「刀剣テレビアニメ」とは
刀剣・日本刀の専門サイト「刀剣ワールド」のコンテンツ「刀剣テレビアニメ」では、時代を1970年代、1980年代、1990年代、2000年代の4つに区分し、刀剣テレビアニメの内容や位置付けが時代の流れと共にどのように変化してきたのかについて、メディアミックスの在り方を軸にして詳しく解説しています。
刀剣テレビアニメの中から、オススメしたい内容を各年代より厳選し、その概要をご紹介します。
1970年代の刀剣テレビアニメ

ロボットテレビアニメブームで育まれた刀剣テレビアニメ
数あるテレビアニメのジャンルの中でも、1970年代に一世を風靡(ふうび)したのが「ロボットテレビアニメ」。
そのブームの火付け役となったのは「マジンガーZ」であり、続編の「グレートマジンガー」では、主人公が用いる主要な武器として剣が用いられています。
その後も様々なロボットテレビアニメで剣が登場することにより、アニメの中の刀剣文化が育まれていったのです。
おもちゃ的なスーパーロボットからリアルロボットへ
本コンテンツの記事「リアル刀剣ロボットテレビアニメの誕生」では、このロボットアニメの対象が子どもから青年層に移った経緯を解説しています。
もともとロボットテレビアニメは、小学生ぐらいの子どもが対象。例えば前述のマジンガーZは、少年向けのマンガ雑誌「週刊少年ジャンプ」で連載されていた作品が原作でした。
しかし、70年代後半になると、中学生以上の青年を視聴者として想定したロボットテレビアニメが放送されるようになります。それは、現在でも多くの大人の根強いファンを持つ「機動戦士ガンダム」です。この作品では、人が乗れる二足歩行ロボットを「兵器」とみなして「モビルスーツ」と呼び、その造形は日本の侍から着想を得たと言われています。
そして、モビルスーツが用いる武器が「ビームサーベル」と称する光線の剣です。機動戦士ガンダムではビームサーベルを使い、武士さながらの迫力満点な殺陣のシーンが頻繁に登場。なかには、薙刀(なぎなた)を模した「ビームナギナタ」とビームサーベルが刀を交えるエピソードもありました。
本コンテンツでは、機動戦士ガンダムで印象的な殺陣のシーンをいくつか紹介しつつ、もともとのロボットアニメが「スーパーロボット」と呼ばれていたところから、機動戦士ガンダムのように戦闘のリアルを追求したものを「リアルロボット」と呼び分けられるようになった経緯も説明しています。
1980年代の刀剣テレビアニメ
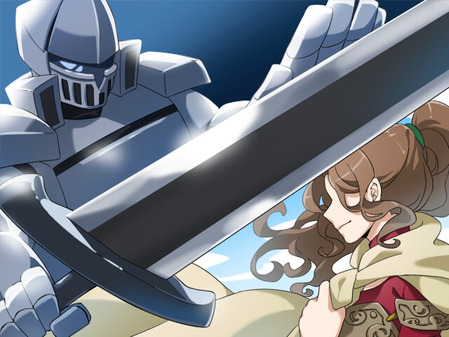
新しい切り口で作られた刀剣テレビアニメの登場
ロボットテレビアニメのブームが落ち着きを見せ始めた1980年代。当時の刀剣テレビアニメにおける大きな特徴は、女性ファンを獲得すべく美少年戦士を登場させたり、ロボットテレビアニメと中世ファンタジーを融合させたりするなど、それまでとは異なる多様な視点で作られたこと。
それらの中で時代を色濃く反映していたのが、「ロールプレイングゲーム」(略称RPG)風の刀剣テレビアニメです。RPGとはキャラクターを操作し、仲間と協力して経験値を上げ、目的を達成するゲームジャンルのひとつ。
1983年(昭和58年)に、任天堂より「ファミリーコンピュータ」が発売されると、「家庭用ゲーム」のブームが到来。剣と魔法を駆使して物語を進めていくRPGは、家庭用ゲームでも人気ジャンルとなっていました。
ゲームとのメディアミックスによる刀剣テレビアニメの発展
「ゲームメディアミックスしていく刀剣テレビアニメ」の記事では、「魔神英雄伝ワタル」(ましんえいゆうでんわたる)を皮切りに続々と登場した、RPGの影響を多大に受けていたテレビアニメ作品を紹介。
魔神英雄伝ワタルは、小学4年生の主人公「戦部ワタル」(いくさべわたる)が異世界で贈られた「勇者の剣」(ゆうしゃのつるぎ)で魔神「龍神丸」(りゅうじんまる)を召喚し、悪の帝王「ドアクダー」退治へ旅立つ物語です。
流行していたRPGの要素を物語構成に上手く導入したこの作品は、家庭用ゲーム機「PCエンジン」用のソフト化に留まらず、「ノベライズ」(ヒットした作品の脚本を小説化すること)や「オリジナル・ビデオ・アニメ」(略称OVA)化などのメディアミックスを積極的に行ったことで、高い人気を博したのです。
この他にも、パソコンゲームやアーケードゲーム(業務用ゲーム)など、様々な種類のゲームから誕生した刀剣テレビアニメについて取り上げています。
1990年代の刀剣テレビアニメ
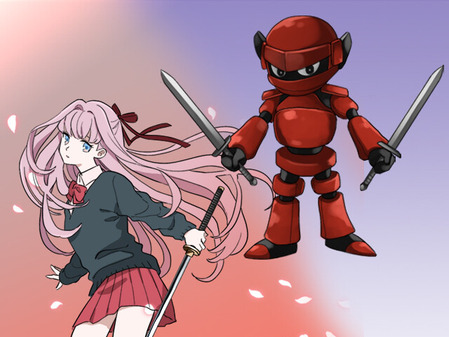
「ちびキャラ」による原点回帰
1990年代に入ると、青年向け志向だったロボットテレビアニメが子ども向けに回帰します。
「ちびキャラ時代の刀剣テレビアニメ」の記事では、対象視聴者をテレビアニメの原点とも言える低年齢層向けに設定した経緯を、複数のロボットテレビアニメを通じて説明。
例えば、1990~1991年(平成2~3年)に放送されたSF時代劇ギャグバトルテレビアニメ「キャッ党忍伝てやんでえ」(きゃっとにんでんてやんでえ)や、時代劇ロボットテレビアニメ「からくり剣豪伝ムサシロード」(からくりけんごうでんむさしろーど)は、ギャク多めの内容もさることながら、ロボットの頭身を低くしてデフォルメした造形の可愛らしさが、子ども達に受けてヒットしました。
それは、当時の少年マンガから始まった「ちびキャラ」ブームが背景にあったと考えられているのです。
新たな試みがなされた刀剣テレビアニメ
1990年代半ばには、本格的な時代劇を題材にしたテレビアニメ「~サンライズ・ネオ・ハイパー・アニメーション~闇夜の時代劇」が制作されています。
CGを駆使する実験的なテレビ番組であったこのシリーズは、「徳川家康」を討とうと葛藤する「伊賀流忍者」について描いた「正体を見る」など、全4作品で構成。それらの中で日本刀が大きく取り上げられているのは、「居合術」(いあいじゅつ)の始祖と伝わる「林崎甚助」(はやしざきじんすけ)を主人公とした「甚助の耳」です。
この作品では、鎌倉時代の名工「粟田口国綱」(あわたぐちくにつな)の作刀が登場。もののけ退治を請け負った林崎甚助が用いる刀として、物語における重要な役割を果たしました。
2000年代の刀剣テレビアニメ

女性ファンの獲得と動画配信による世界進出
「萌え」などの言葉が流行したことからも分かるように、2000年代は、いわゆる「同人文化」(どうじんぶんか)が一般的にも普及した時代。
例えば、刀剣テレビアニメのジャンルでは、女性ファンを意識した美しい青年剣士が登場する「鋼鉄三国志」(こうてつさんごくし)が地上波の深夜帯に放送されており、同人文化から強い影響を受けていることが窺えるのです。
本コンテンツの「世界同時動画配信時代の刀剣テレビアニメ」では、2000年代が、アメリカで動画共有プラットフォーム「YouTube」が誕生したことを皮切りに、様々な動画配信サービスが始まった時代であることについて言及しています。
日本においても「GyaO」(ぎゃお:現在のGYAO!)や「ニコニコ動画」などの動画配信のプラットフォームがいっせいに登場。これにより、スマートフォンやパソコンがあれば、日本のテレビアニメを世界中で観られるようになったのです。
本コンテンツでは、動画配信された刀剣テレビアニメの一例として「幕末機関説 いろはにほへと」を取り上げています。これは、剣客浪人「秋月耀次郎」(あきづきようじろう)が「戊辰戦争」(ぼしんせんそう)を背景に、「覇者の首」の封印を目的に旅をする物語です。
「坂本龍馬」(さかもとりょうま)や「勝海舟」(かつかいしゅう)など、実在した幕末の志士が登場し、物語の展開における重要な役割を担っているのも見どころのひとつです。
刀剣テレビアニメを通じて刀剣の世界を堪能しよう!
刀剣ワールドのコンテンツ、刀剣テレビアニメをご覧いただければ、刀剣テレビアニメが発展した背景に、ロボットアニメという意外な存在があったこと、そしてメディアミックスにより、高い人気を得てきたことが分かるようになっています。
刀剣とアニメが両方とも好きな人はもちろん、どちらかにのみ興味がある人にも、楽しく読んでいただけるコンテンツです。
本コンテンツを通してお気に入りの刀剣テレビアニメを見付けて実際に観ることで、奥深い刀剣の世界を味わってみてはいかがでしょうか。