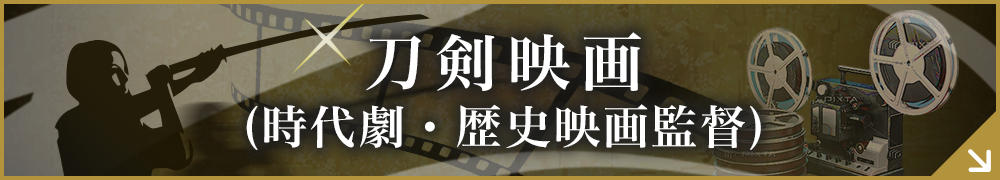刀剣映画(歴史映画監督)の紹介 - 刀剣ワールド
- 小
- 中
- 大

刀剣ファンや歴史愛好家には、「刀剣・歴史映画は見逃せない!」という方も多いのではないでしょうか。刀剣・歴史映画は「時代劇」と総称され、日本映画草創期からの人気コンテンツです。そのなかで描かれる勧善懲悪や忠義、ときには裏切りの人間ドラマ、また、チャンバラと呼ばれる剣闘シーンが観客を魅了し続けています。
刀剣映画(歴史映画監督)で名作を発見!
刀剣ワールドのコンテンツ「刀剣映画(時代劇・歴史映画監督)」では、日本の代表的な映画監督33人を「戦後昭和生まれ」、「戦前昭和生まれ」、「明治・大正生まれ」に分けてご紹介。それぞれの映画監督のプロフィールと手がけた刀剣・歴史映画を解説しています。
ご紹介する刀剣・歴史映画は、モノクローム時代の古典的傑作から、今が旬の俳優が魅力的な近作まで100作以上。まだ見ぬ名作との出会いが期待できるコンテンツです。
戦後昭和生まれの刀剣・歴史映画監督
刀剣映画(時代劇・歴史映画監督)では、最も若い戦後昭和生まれの刀剣・歴史映画監督と作品から紹介し始めます。この世代の映画監督は、アイドルや芸人を主要キャストに起用し、彼らの新しい魅力を引き出すのが得意です。
映画ジャーナリスト出身・原田眞人の「関ケ原」
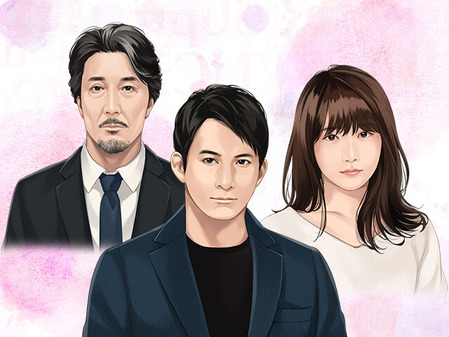
原田眞人(はらだまさと)は、イギリスやアメリカで映画ジャーナリストとして活動しながら映画制作を学びました。監督デビュー前に、俳優としてハリウッド映画【ラストサムライ】(2003年〔ワーナー・ブラザース〕配給)に出演しているユニークな経歴の持ち主です。
原田眞人は、念願だった司馬遼太郎作品の映画化を【関ヶ原】(2017年〔東宝/アスミック・エース〕配給)で実現しました。主人公の「石田三成」を演じたのは、当時、アイドルグループ「V6」のメンバーだった岡田准一さんです。
石田三成が「関ヶ原の戦い」で「徳川家康」(演:役所広司)に敗れて処刑されるまでと、勝敗を決した「小早川秀秋」(演:東出昌大)の裏切りの動機を描きます。
ヒットメーカー・三池崇史の「十三人の刺客」
三池崇史(みいけたかし)は横浜放送映画専門学院(現・日本映画大学)を卒業後、1991年にビデオ映画「突風!ミニパト隊」で監督デビューしました。「依頼が来た順に引き受ける」と公言する通り、コメディ、バイオレンス、ホラーなどジャンルを問わず制作し、安定した観客動員数を獲得しているヒットメーカーです。
三池崇史は2010年に、工藤栄一監督作の時代劇映画【十三人の刺客】(1963年〔東映〕配給)のリメイクに挑んでいます。リメイク版では、暴虐非道のふるまいを繰り返す播磨国明石藩の藩主・松平斉韶(まつだいらなりつぐ)を、当時アイドルグループ「SMAP」のメンバーだった稲垣吾郎(いながきごろう)さんが好演して話題になりました。
この暴君・松平斉韶を、わずか13人で討ち取ろうと決起した旗本・島田新左衛門(演:役所広司)と、藩主を守り抜こうとする家臣・鬼頭半兵衛(演:市村正親)の対決は見せ場です。
戦前昭和生まれの刀剣・歴史映画監督

戦前生まれの刀剣・歴史映画監督は、テレビが娯楽の主役になっていった時代に、映画ならではの表現に取り組みました。テレビ時代劇で人気を博した、正義の味方が悪漢をこらしめるシリーズとは一味違う、死や憎しみをリアルに描く作風が特徴です。
女性映画の名手・五社英雄が描く男の絆「三匹の侍」
五社英雄(ごしゃひでお)は、【鬼龍院花子の生涯】(1982年〔東映〕配給)や【吉原炎上】(1987年〔東映〕配給)など、苦界に生きる女性が主人公の作品で知られますが、出世作はフジテレビ在籍時代に企画したテレビ時代劇【三匹の侍】(1963~1969年〔フジテレビ〕系列)でした。殺陣のシーンに入る、刀と刀がぶつかり合う効果音は、五社英雄が【三匹の侍】で初めて用いた演出です。
五社英雄が制作したテレビ時代劇【三匹の侍】は、高視聴率を上げて映画化が決まり、これが五社英雄の監督デビュー作になりました。
映画版【三匹の侍】(1964年〔松竹〕配給)では、代官の悪政に抗う百姓達を抑え込むために雇われた浪人の柴左近(演:丹波哲郎)と桜京十郎(演:長門勇)、代官の用心棒・桔梗鋭之介(演:平幹二朗)が出会い、百姓側に味方しようと意気投合します。
この3人は途中で離脱したり、寝返ったりしながらも、最後は団結して代官を追い詰めるのでした。物語の終盤、命乞いする代官に柴左近が放つ言葉「百姓とて人間だぞ、無宿の浪人とて同じように人間だということを思い知れ!」は、本作品を貫くテーマです。
明治・大正生まれの刀剣・歴史映画監督

明治・大正生まれの刀剣・歴史映画監督は、剣豪スターを主人公に躍動的なチャンバラ映画を量産しました。戦後は、三船敏郎・勝新太郎・仲代達矢らの新しいスターを見出し、愚かさや狡さも持つ人間くさい武士を演じさせています。
4度リメイクされたマキノ雅弘の「浪人街」
マキノ雅弘(まきのまさひろ)は、「日本映画の父」、「チャンバラ映画の創始者」と言われるマキノ省三の息子です。マキノ雅弘の初期の代表作【浪人街】(1928年〔マキノ・プロダクション〕配給)は、自身が3回リメイクし、4回目のリメイクでは総監修を務めています。
【浪人街】を制作した当時のマキノ・プロダクションは、スター俳優が集団退社して窮地に立たされていました。このためマキノ雅弘は、本作の主要キャストである4人の浪人役に無名の若手俳優を起用しています。
この浪人4人は、母衣権兵衛(ほろごんべい:南光明)、荒牧源内(あらまきげんない:谷崎十郎)、赤牛弥五右衛門(あかうしやごえもん:根岸東一郎)、土居孫左衛門(どいまござえもん:河津清三郎)で、同じ長屋に住む仲間です。
荒牧源内の妻・お新(演:大林梅子)が旗本に追われる身になり、浪人4人はお新を救おうと団結しますが、赤牛弥五右衛門は旗本に買収されて仲間を裏切ります。しかし、旗本一味と闘う仲間を見捨てられず、助太刀に飛び込むのです。
「おのれ裏切ったな!」とののしる旗本に、赤牛弥五右衛門が「馬鹿ッ、表返ったのじゃわッ!」と言い返す場面では、上映中に歓声が上がり、拍手が起きたと言われています。
三船敏郎とは名コンビ・稲垣浩の「大坂城物語」
稲垣浩(いながきひろし)の父は新劇俳優で、自身も幼少期には舞台に立ち、17歳で俳優として日活に入社すると映画主演も果たしました。
映画監督に転身後は、中里介山原作の【大菩薩峠】(1935年〔日活〕配給)や吉川英治原作の【宮本武蔵】(1954年〔東宝〕配給)を映像化して、時代小説の映画化の先駆けになります。
稲垣浩は俳優・三船敏郎と何度もコンビを組んでおり、村上元三原作【大坂城物語】(1961年〔東宝〕配給)も三船敏郎主演です。本作の主人公は、徳川家康が豊臣秀吉の遺児・豊臣秀頼を攻めた大坂冬の陣で、豊臣方に付く浪人・茂兵衛(もへい:三船敏郎)。田舎者の茂兵衛は、大坂城のスケールの大きさに惚れ込んで豊臣方に味方すると決意し、命がけの活躍をします。
茂兵衛が魅せられた大坂城を20分の1サイズで精巧に再現したのは「ウルトラマン」シリーズの生みの親で「特撮の神様」と呼ばれた円谷英二(つぶらやえいじ)で、これも本作の見どころのひとつです。