偉人・有名人と日本刀の意外な関係 - 刀剣ワールド
- 小
- 中
- 大

刀剣・日本刀に関係のある偉人・有名人って誰かいるのかな?そう思って調べていたら、とっても面白いエピソードを持つ、刀剣・日本刀に関係の深い偉人・有名人が分かりました!元プロ野球選手の「王貞治」さんや昔話に出てくる「一休」さん、明治維新の立役者である「坂本竜馬」や「木戸孝允」です。誰もが知っているこれらの偉人・有名人と刀剣・日本刀の意外な関係とは?
王貞治さんが振っていたのは野球バットじゃなくて日本刀だった?
日本刀を持った有名人が新聞の1ページに
新聞をパラパラとめくっていると、ある面白い記事を見付けました。そこに書いてあったのは、王貞治(おうさだはる)さんのプロ野球選手時代のこと。プロ野球選手として、パッとしない暗黒時代を3年ほど経験していた頃、大打者へと育てるために、とあるコーチが命がけの特訓をさせました。
命がけの特訓をさせるのに使用したのは、バットではなく日本刀(本物)。

日本刀で練習している王貞治さん
日本刀で練習させたのは誰?
日本刀を持って練習させたのは、1962年(昭和37年)に打撃コーチに就任した荒川博(あらかわひろし)さんです。
彼は日本刀とバットの「振り方」がとても似ていることに気付きました。

バットを振る
命がけの練習が王貞治さんを変えた!
バットを日本刀に変えることを想像してみて下さい。まず、本物なので少しでもズレたら大怪我を負いかねません。一歩間違えたら死ぬことだってあります。このような危険さを抱えながら、王貞治さんは天井に吊された新聞紙を、日本刀で切る練習をスタート。
これにより、王貞治さんが学んだのは、日本刀が切れる理屈として「角度が少しでもズレたら切れないこと」や「一度止めてから切らないと切れない」ことなど。
彼はこれを活かし「一瞬の間」を学びます。
野球のバットを構えたときにも「今だ!」という間が分かったそうです。
バットを日本刀に変えることで特に学んだことは、命がけで何かに取り組むこと。
これって、実は何事においても大切なのかもしれませんね。
一休さんと日本刀のお話
真っ赤な鞘(さや)と木刀
「一休さん」と言えば、小坊主が、得意のトンチを生かして、身の回りで発生している様々な問題を解決していくイメージ。それは、アニメの一休さんの影響が大きいのかもしれません。
しかし、実物の一休さんは…。無精ひげにボサボサの頭髪。およそ仏に仕える禅僧とは思えない容貌でした。それは行動にも現れていました。肉食や飲酒をはじめ、戒律で禁じられていたことは大抵、やり尽くしていたと言われています。今で言うところの「破天荒」という言葉がピッタリの存在だったと言えるでしょう。そんな一休さんには、日本刀にまつわる逸話もありました。
僧侶と日本刀。一見すると、似つかわしくない組み合わせとも思えます。でも、そんなことはありません。日本刀の「五箇伝」(ごかでん)のひとつ「大和伝」(やまとでん)における「大和五派」(やまとごは)。その最古の流派である「千手院派」(せんじゅいんは)は、奈良の大仏で有名な、あの東大寺に隷属して僧兵のために日本刀を供給していたのです。
このように寺院は、お抱えの刀鍛冶によって独自の武器供給ルートを確保していました。その結果、平安時代末期には強大な軍事力を有するようになり、寺院同士の勢力争いがあったのはもちろん、朝廷や摂政など「国家権力」に対しても、軍事力を背景として強硬に要求を突き付けるように。大和伝の流派の名前は、ほとんどが寺院の名前に由来した物でした。
話をもとに戻しましょう。あるとき、一休さんは、立派な赤い鞘(さや)に入った日本刀を差して堺の町を闊歩(かっぽ)。不思議に思った人から「なぜ刀を持っているのですか」という質問を受けると、おもむろに日本刀を抜いたのです。しかし、鞘の中身は、何の変哲もないただの木刀…。
啞然(あぜん)とする質問者に、一休さんはこう言い放ちました。「近頃の偉い坊さんは、これと同じだ。派手な袈裟(けさ)を着て、外見はやたらと立派だが、中身はこの通り、何の役にも立たない。飾っておくしか、使い道はないのだ」と。いわゆる高僧達が、見かけ倒しになっていた状況を一刀両断したのでした。
物事の本質を突いた鋭い言葉に、背筋がピンと伸びた気がします。

一休さんと日本刀
坂本竜馬と木戸孝允、2人の偉人と日本刀
史料が語る「幻の試合」の意外な結末
木戸孝允(きどたかよし)は、意外にも?「神道無念流」(しんどうむねんりゅう)免許皆伝の剣豪でした。そうは言っても、超一流の剣の達人に勝てるほどの腕だったのか?という疑問が湧いてくるのは当然の話ですよね。そんな疑問に答えを出すことができる日が来るかもしれません。
2017年(平成29年)10月、群馬県前橋市にある「群馬県立文書館」で、「桂小五郎」(かつらこごろう:のちの木戸孝允)と坂本龍馬が対戦し、3対2で龍馬が敗れたことを記録している史料が見つかったのです。
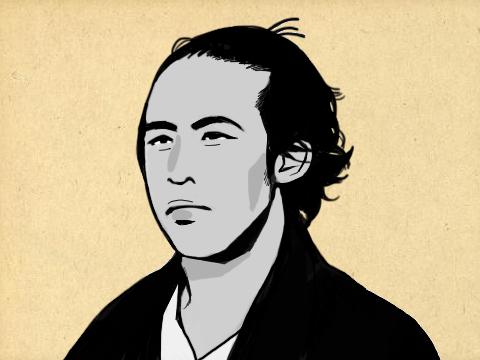
坂本龍馬
史料によれば、両者が対戦したのは、1857年(安政4年)3月1日、江戸の土佐藩上屋敷で行なわれた土佐藩主「山内豊信」(やまのうちとよしげ:号・容堂)の上覧試合でのこと。この試合については、これまでも様々な史料に記載がありました。しかし、開催時期や「木戸」の名前などの点で、史実との間に食い違いがあり、否定的な意見が多かったのです。言ってみれば「幻の試合」。でも、今回の史料に照らせば、どうやら本当っぽい…ということになっています。
もし本当だったとしても、龍馬が本気じゃなかっただけ?
そんなことはありません。龍馬は当時、土佐藩士(脱藩したのは1862年[文久2年])で、会場は土佐藩の上屋敷。見守った容堂は主君に当たります。その試合で負けることは、主君に恥をかかせてしまうということ。状況的には「ガチ」で試合をした可能性が限りなく高いのです。
龍馬と言えば、猛者ぞろいだった「北辰一刀流」(ほくしんいっとうりゅう)の千葉道場で塾頭を務めたと言われているほどの剣の達人。「維新三傑」のひとりである政治家が、本当に勝っちゃっていたとしたら…。検証が進んでいくのが楽しみです。



























