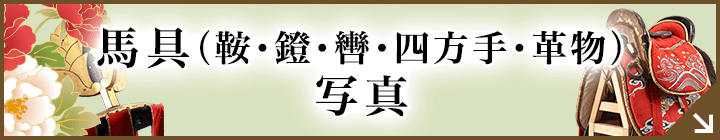戦国武将お祭り【相馬野馬追】 - 刀剣ワールド
- 小
- 中
- 大

夏の盛りを迎える7月27日(土)、28日(日)、29日(月)の3日間に亘って行なわれた「相馬野馬追」(そうまのまおい)。今年は、福島県の相馬市と南相馬市を訪ね、勇壮なお祭りを観覧することができました。 3日間を通してほぼ晴天に恵まれ、昼間の気温は35℃前後となる猛暑。そんな中、たいへん多くの観客が足を運び、文字通り熱いイベントとなったのです。
相馬野馬追とは

相馬太田神社
「相馬野馬追」(そうまのまおい)は、毎年7月最終週の土・日・月曜日に福島県相馬市、南相馬市で開催されるお祭りで、国の重要無形民俗文化財に指定されています。
起源は相馬氏の遠い祖先にあたる「平将門」(たいらのまさかど)までさかのぼり、放った野生馬を敵兵に見立てて軍事訓練を行なったのが始まりと言われ、その歴史はおよそ1,000年。
幕末から明治時代初めの「戊辰戦争」で、相馬氏が治めていた中村藩が明治政府に敗れると、野馬追も消滅の危機を迎えますが、「相馬太田神社」(そうまおおたじんじゃ)が中心となって再興。
お祭り2日目のハイライトである「甲冑競馬」と「神旗争奪戦」(しんきそうだつせん)は、戊辰戦争以降に誕生した行事であるとのことです。
そんな長い歴史を持つ相馬野馬追を、日にち順にご紹介しましょう。
1日目:宵乗り
出陣式
相馬野馬追は、1日目の「出陣式」から始まります。
「相馬中村神社」には相馬市の宇多郷(うだごう)勢、相馬太田神社には南相馬市原町区の中ノ郷(なかのごう)勢、「相馬小高神社」には南相馬市小高区の小高郷(おだかごう)・双葉郡の標葉郷(しねはごう)勢が、それぞれ武者装束に身を包んで参陣。
空気を震わせるような螺(つぶ/にし:巻き貝の古名)の音を合図に、総大将を擁する相馬中村神社では、ひときわ厳かな雰囲気の中で出陣の儀式が行なわれました。

螺役
今年の総大将は、「相馬行胤」(そうまみちたね)氏。相馬家33代当主「相馬和胤」(そうまかずたね)氏の長男で、3年連続で総大将を務めているそうです。また、令和初の開催ということもあり、次男の「相馬陽胤」(そうまきよたね)氏と兄弟揃っての出陣となりました。
杯を掲げて祝杯を挙げ、準備が整うと、大将の命令一下、いざ出陣。詰め掛けた観客の拍手に送られながら、南相馬市原町にある「雲雀ヶ原祭場地」(ひばりがはらさいじょうち)へ向けて騎馬武者が列を成して進んでいきます。
甲冑(鎧兜)を身に付け、おのおの背中に旗指物(はたさしもの)を掲げた騎馬武者の大行列が街中を闊歩する姿は勇壮そのもの。沿道を埋めた観客からは拍手が起こり、多くの方が行列を写真に収めていました。
総大将御迎
その頃、南相馬市鹿島区にある「北郷陣屋」(きたごうじんや)では、総大将を迎える「総大将御迎の儀」(そうだいしょうおむかえのぎ)のための陣が張られ、緊張感すら漂っています。
やがて、総大将が率いる宇多郷勢が到着。ここでも螺の音が響き渡り、古式にのっとった儀式が執り行なわれました。
儀式に参加する武者の中には子ども達の姿もあり、堂々たるかわいさを発揮。巧みに馬を乗りこなす子ども騎馬武者も目を引いていました。この暑さのもとでの武者装束は、身体に負担がかかるのではないかと心配しましたが、子ども達は終始背筋を伸ばして凛々しい表情。心配はいらなかったようです。
総大将御迎の儀を終えた一行は、宇多郷勢と北郷勢が合流し、一団となって雲雀ヶ原祭場地を目指します。
宵乗り競馬
雲雀ヶ原の相馬野馬追祭場地には、宇多郷・北郷勢、中ノ郷勢、小高郷・標葉郷勢の3軍が終結。ここでは、古式競馬が行なわれます。
相馬太田神社の宮司によって馬場清めの儀式があり、ずらりと並んだ螺役が一帯に鳴り響かせると「宵乗り競馬」(よいのりけいば)の開始です。
白鉢巻(しろはちまき)に野袴(のばかま:武士が旅に用いた袴)、陣羽織(じんばおり)といういでたちに、古式馬具を付けた騎馬武者が5騎、1周1,000mの馬場を疾走します。土煙を上げながら駆け抜ける競馬は荒々しく、迫力満点! 蹄(ひづめ)が跳ね上げた土の匂いと、騎馬武者達の熱気が伝わってくるようです。
観客は、祭場地全体を見渡せる本陣山の斜面に腰を下ろして観戦。まだ1日目で、観客席は満員ではありませんでしたが、拍手の音は大きく、祭りの熱気に包まれて宵乗り競馬は終了しました。
2日目:本祭り
お行列
夏の空にとどろく花火を合図に2日目がスタート。鳴り響く螺の音と陣太鼓が出発の時を告げます。
相馬太田神社(中ノ郷勢)を先頭に、相馬小高神社(小高郷・標葉郷勢)、総大将を擁する相馬中村神社(宇多郷・北郷勢)の順で出立。総勢500騎を超える騎馬武者が、雲雀ヶ原祭場地へ向かって約3kmを行軍します。
騎馬武者のほとんどが甲冑(鎧兜)に身を固めて太刀を佩き、先祖伝来の旗指物を翻しての戦国絵巻は、1日目の行列を上回る迫力。
沿道から見入っていても、その圧倒的な華々しさに気圧されるようでした。拍手と歓声で、街全体が沸きかえっていたのです。
甲冑競馬

旗指物を背にした騎馬武者
行列が雲雀ヶ原祭場地へ到着すると、神輿(みこし)を御本陣に安置し、式典が行なわれます。芝の観客席は、すでにほぼ満席です。夏の日差しを避けるように日傘がそこここで開き、扇子や団扇(うちわ)がぱたぱたと振られ、開始のときを待っています。
そして、螺の音が響き、甲冑競馬の開始となりました。
甲冑競馬は、1周1,000mの馬場を10頭立てで競います。これを10回開催。参加する騎馬武者は兜を脱いで白鉢巻を締め、代々伝えられた旗指物を背に、自慢の駿馬(しゅんめ)を疾走させるのです。
馬場の状態のためか、10頭がせめぎ合ったためか、跳ね上げられた土を全身に被ってしまう騎馬武者がいたり、旗指物が横倒しになってしまったりすることもありました。地響きと共に、競馬の激しさが伝わってきます。観客も声を限りに声援を送っていました。
神旗争奪戦
続いて行なわれたのは神旗争奪戦(しんきそうだつせん)で、これは打ち上げられた花火の中から舞い落ちてくる御神旗を、騎馬武者達が奪い合う行事です。
螺の音を合図に、騎馬武者達が馬場中央部の雲雀ヶ原へ乗り入れます。約500騎の騎馬武者が優位なポジションを求めて先を争い、すでに陣取り合戦の様相。
花火1発ごとに2本の御神旗が上げられると、舞い降りる地点を目指して騎馬武者が殺到しました。馬を操りながら押し合い圧し合いする様は、太刀こそ使わないものの、激しい合戦を彷彿とさせます。落馬してしまう武者もおり、スリルもひとしおです。

神旗争奪戦
御神旗を勝ち取った騎馬武者は、御神旗を頭上へ掲げながら、つづら折りとなった「羊腸の坂」(ようちょうのさか)を駆け上がり、本陣山の山頂へ。
御神旗は、敵の首に見立てているため、審査が行なわれ、その後、勝者は神社からの御礼と副賞を受け取って戻ります。羊腸の坂の周りを囲む観客からは、惜しみない拍手が送られていました。
花火は合計20回。なお、打ち上げられる御神旗は、相馬中村神社が青色、相馬太田神社が赤色、相馬小高神社が黄色となっているため、一目で見分けがつきます。
帰り馬
これら一連の行事を終えた各隊は、原町区の中ノ郷勢を除いて地元へ帰還することに。
オレンジ色に染まった夕日を浴びながら、騎馬武者の行列が街を行進していきます。武者達の表情には達成感と笑みがあふれていました。
なかには、子ども武者を前に乗せて帰る騎馬武者の姿も。沿道の観客からの拍手が温かく包み込んでいました。
3日目:野馬懸
「野馬懸」(のまかけ)とは、多くの馬の中から神意に適う馬を捕らえ、奉納するという神事です。
蝉の声が降り注ぐ小高区の相馬小高神社に、蝉に負けないくらいの螺の音が響きます。その境内に設けられた竹矢来(たけやらい:竹を組み合わせて作った囲い)へ、騎馬武者達が裸馬(鞍などの馬具を着けていない馬)を追い込んできました。
計3頭を追い込むと、白鉢巻に白装束を纏った「御小人」(おこびと)と呼ばれる数十人の若者が馬を捕らえんと挑むのです。
まず、最も強そうな馬に、御神水に浸した「駒とり竿」で御印を付けるのですが、この竿は人の背丈の何倍もあり、なかなか思うように付けることができません。馬が逃げてしまって、駒とり竿が空振りするたびに、竹矢来を囲んだ観客から「惜しい!」という声が上がっていました。
1頭の馬に御印を付けることができると、御小人衆が総がかりとなって、この馬を素手で捕まえます。走り回る馬の首にしがみ付き、たてがみを掴んで止めようとしますが、馬の力に負けて地面に転がされてしまう御小人も。数人で馬の首を押さえ、なおも後ずさりして逃れようとする馬を宥めて、ようやく捕らえることができました。
こうして、第1番に捕らえた馬を、神馬として相馬小高神社に奉納。相馬地区の平和と安寧(あんねい)、繁栄を祈願します。神馬のたてがみには、奉納の印として紙垂(しで)が付けられました。この野馬懸の神事が絵馬の起源とされ、国の重要無形民俗文化財に指定される理由になったとのことです。
奉納された馬以外の2頭は、捕らえて「お競りの儀」にかけます。博労(ばくろう:馬や牛の売買を仲介する人)が競り落として野馬懸が終了。
こうして、3日間に亘る相馬野馬追祭りは、感動の余韻を残して幕を閉じたのです。
迫力に圧倒された3日間
相馬野馬追を直に観たのは初めてだったのですが、騎馬武者の勇ましい姿と、たくさんの疾走する馬の迫力に、終始圧倒されっぱなしでした。
神旗争奪戦は、まさに目の前で繰り広げられる戦国合戦図。また野馬懸では、不謹慎とは思いつつ、馬に翻弄される人の様子に笑ってしまう場面もありました。
歴史ファンには、実際に足を運んで観る価値あり! ただ、夏の昼間に行なわれるお祭りですので、万全の暑さ対策はお忘れなく!