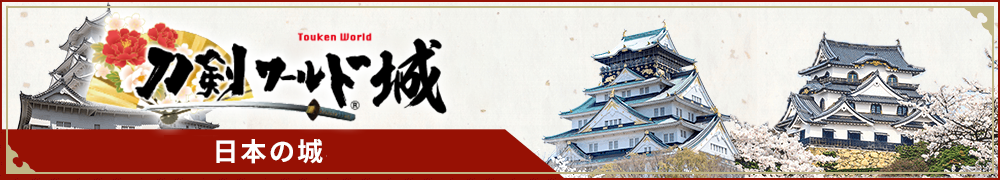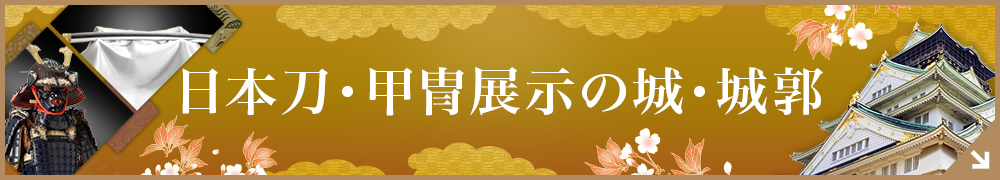大阪の城 - 刀剣ワールド
- 小
- 中
- 大

近畿地方の経済・文化の中心地として京都に次いで栄えてきた大阪府。同地には、「大阪城」や「千早城」、「岸和田城」、「飯盛山城」等の城跡があることで知られています。
鎌倉時代末期から安土桃山時代頃にあった大阪の城。それぞれの歴史や特徴について、ご紹介していきます。
大阪城(大阪府大阪市中央区)

大阪城
1583年(天正11年)頃、天下人「豊臣秀吉」によって築城された「大阪城」。別名「金城/錦城」(きんじょう)。
1582年(天正10年)に、「織田信長」が「本能寺の変」で討ち取られた翌年から築城が開始され、わずか1年半後に天守閣が完成したと伝わっています。
城の周辺は、南方以外は川や海に囲まれていたため守りが堅く、難攻不落の城として名を馳せました。
政敵「徳川家康」に落城を狙われるも、なかなか陥落しなかったことで知られますが、1614年(慶長19年)の「大坂冬の陣」において講和条件として惣構(そうがまえ)・三の丸・二の丸を取り潰され、裸城にされたことをきっかけに、1615年(慶長20年)の「大坂夏の陣」にて落城。この出来事により豊臣家は滅亡し、徳川家による統治が始まりました。
現在は、「日本100名城」や国の特別史跡に指定されており、「太閤さんのお城」と呼ばれている他、博物館「大阪城天守閣」として一般にも広く親しまれています。
豊臣秀吉のエピソードや、関連のある刀剣をご紹介!
歴史を動かした有名な戦国武将や戦い(合戦)をご紹介!
歴史上の人物が活躍した合戦をご紹介!
武将達が戦った全国各地の古戦場をご紹介!
徳川家が改築した大阪城
豊臣家の滅亡後、大阪城は徳川家の管理下におかれ、改築されました。
もとの石垣と堀は取り潰され、盛り土の上に石垣が積みなおされたと伝わっています。
これにより豊臣家の大阪城跡は地中に埋もれ、天守閣も独自の物に造り替えられたため、改築後の大阪城は「徳川大阪城」、改築前の大阪城は「豊臣大阪城」と呼ばれ区別されるようになりました。
千早城(大阪府南河内郡千早赤阪村大字千早)

千早城址
1332年(元弘2年)、「楠木正成」(くすのきまさしげ)によって築城された「千早城」。別名「金剛山城」(こんごうさんじょう)は、「楠木七城」(くすのきしちじょう)と言われ、楠木正成が後醍醐天皇の命を受け、鎌倉幕府への攻撃の拠点とするために築城した7つのお城のひとつで、楠木正成の「詰の城」(つめのしろ:武将が領国内に設けた最終拠点の城)だったことで知られています。
城の背後のみ金剛山に繋がっており、これを除く四方のほとんどを絶壁が囲む好立地により、難攻不落を誇りました。
南北朝時代の軍記物語「太平記」によると、1333年(元弘3年)に起こった「千早城の戦い」における鎌倉幕府軍の数は、およそ20~100万と記述されており、小学館の「赤坂・千早城の戦い」では、数万から10万が妥当と記載されているなど諸説ありますが、大勢の鎌倉幕府軍に対して、1,000人足らずの楠木軍で約3ヵ月半篭城し、幕府軍の撤退まで堪えきったと記されています。
現在は日本100名城や国の史跡に指定されており、城跡として一般にも親しまれています。
武将達が戦った全国各地の古戦場をご紹介!
3ヵ月半の篭城戦

楠木正成
千早城と言えば、楠木正成の数々の奇策により、3ヵ月半にも亘った篭城戦が有名です。
1333年(元弘3年)、上赤坂城で勃発し千早城へ持ち越した千早城の戦いでは、100万の軍勢が攻め寄せる中、櫓(やぐら)から大石を投げ落とし応戦。混乱する幕府軍に矢や石つぶてを浴びせることで、多くの敵を討ち取りました。
また、幕府軍は水源を断つ持久戦をしかけましたが、楠木正成は城内に大木を切り抜いたおよそ300もの木船を設置し、水を溜めていたため事なきを得たと伝わっています。
戦いが続き、敵軍の士気の低下を見た楠木正成は、さらに奇策を講じました。なんと甲冑を着せたわら人形を数10体作らせ、弓や槍を持たせて城外の麓に並べたのです。そして、わら人形の背後に忍ばせた軍勢500人に、夜ごと叫び声を上げさせました。
これを見た鎌倉幕府軍は、楠木軍の決死の攻撃と勘違いし、わら人形めがけて進軍。
楠木軍はまんまとおびき寄せた幕府軍に弓を射かけながら後退し、投石を浴びせることでさらに多くの幕府軍を討ち取ったと伝わっています。
楠木正成のエピソードや、関連のある刀剣をご紹介!
岸和田城(大阪府岸和田市岸城町)

岸和田城
1334年(元弘4年)に、楠木正成の甥とされる「和田高家」(わだたかいえ)が野田町に築城した城を起源とする「岸和田城」は、1394~1428年頃(応永年間頃)に現在の場所へ移築されました。
本丸と二の丸を連ねた形状が「縢」(ちきり:機に使用する縦糸を巻く器具)に似ていることから、別名「千亀利城」(ちきりじょう)とも呼ばれています。
楠木氏の他、和泉守護細川氏や松浦氏、織田氏、中村氏が城主となったのち、1585年(天正13年)には、豊臣秀吉の紀州討伐に際して豊臣秀吉の伯父「小出秀政」(こいでひでまさ)が城主となり、本丸を改修しました。
その後、小出氏から松平氏、岡部氏と城主が変わる中、「岡部宣勝」(おかべのぶかつ)による大改築を受け、その後岡部氏13代が居城したと伝わっています。
1827年(文政10年)に天守は落雷に遭って焼失し、再建されないまま1871年(明治4年)に廃城してしまいましたが、1954年(昭和29年)に再建。
現在は、大阪府の史跡に指定されており、「続日本100名城」にも選定され、人々に親しまれています。
岸和田城天守閣で結婚式
岸和田城は、別名千亀利城(ちきりじょう)とも呼ばれているため、「契り」とかけて縁結びとしても知られているスポット。
天守閣では、岸和田市観光振興協会とホテルサンルート関空の主催・運営により、2005年(平成17年)より和装の人前結婚式を執り行なうことができるようになりました。
現在までに100組以上が挙式しており、和装で結婚式を挙げる人々に熱い支持を得ています。
飯盛山城(大阪府大東市北条・大阪府四條畷市)
「飯盛山城」(いいもりやまじょう)、別名「飯盛城」は、1334~1338年頃(建武年間頃)に北条一族の「佐々目僧正憲法」(ささめそうじょうけんぽう)によって築城されたと考えられていましたが、近年の研究によるとこの根拠となっていた書物「河内志」(かわちし)に記載されている飯盛山城は、紀伊国(きいのくに:現在の和歌山県・三重県南部)にある別の城を指しているとする説も出てきています。
現在では、畠山氏に仕える河内守護代「木沢長政」(きざわながまさ)による築城とする説が有力です。
飯盛山城が築かれた標高約314mの飯盛山は、河内国(かわちのくに:現在の大阪府東部)と大和国(やまとのくに:現在の奈良県)の国境となっていた「生駒山脈」(いこまさんみゃく)の北西に位置しており、城郭史上でも重要な位置にありました。
多くの戦いを経て、城主は木沢氏から三好氏へ移り、1576年(天正4年)に織田信長軍の攻撃を受け廃城。
現在は続日本100名城に選定され、城跡として一般にも親しまれるようになりました。
石垣で固めた史上初の城
現在、飯盛山城は2016~2018年(平成28~30年)に行なわれた発掘調査の結果、広い範囲に石垣が見付かったことで注目を集めています。
築城に石垣を用いる手法は、1576年(天正4年)に織田信長によって築城された安土城が最初と考えられてきましたが、飯盛山城がより早く築城に石垣を採用していたことになるのです。石垣を採用した史上初の城、飯盛山城の更なる研究が期待されています。