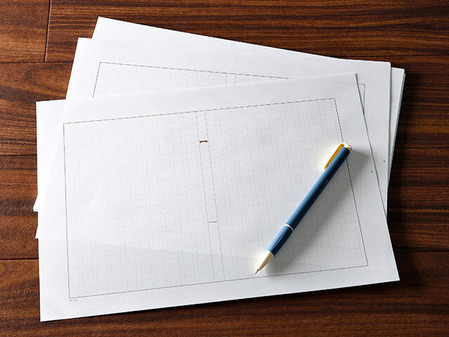刀剣ファン必読の「刀剣小説」 - 刀剣ワールド
- 小
- 中
- 大

日本史に詳しい刀剣ファンのみなさんなら、面白い刀剣小説・歴史小説を手に取ってみたいと思うのではないでしょうか。時代物ならではの古風で趣ある文章や、真剣勝負に挑む剣豪の心理描写など、映像コンテンツや漫画とはまた一味違った表現に心を掴まれること間違いありません。
「でも、どんな小説を選べばいいのか分からない……」
そんなときは、「刀剣ワールド」の「刀剣小説」紹介ページがおすすめです!
刀剣ワールドの大注目コンテンツ刀剣小説
戦後生まれの刀剣小説家
奥州藤原氏に焦点をあてた「炎立つ」
高橋克彦氏は「写楽殺人事件」で、1983年(昭和58年)に第29回江戸川乱歩賞を受賞。
1991年(平成3年)には、表題作の「緋い記憶」を含む短編集で第106回直木三十五賞を受賞しました。そして、「炎立つ」(ほむらたつ)で奥州藤原氏の盛衰を書いています。
奥州藤原氏は、陸奥国(現在の東北地方北東部)と出羽国(現在の山形県、秋田県)を支配した大豪族です。「源頼朝」と対立する「源義経」を匿ったものの、当主の代替わりをきっかけとして源頼朝の圧力に屈し、源義経を自害へ追い込んでしまいます。
しかし、最終的にはその源頼朝に滅ぼされるという悲劇的な運命をたどりました。
どちらかと言えば、源義経や源頼朝など、華々しい武将達の脇役になりがちな奥州藤原氏ですが、この炎立つでは主役の一族として
フォーカスされ、1993年(平成5年)には、NHKの大河ドラマにもなっているのです。
刀剣小説の解説では、岩手県釜石市生まれの高橋克彦氏が、故郷の岩手県に向き合い続ける姿勢について解説。独自の視点で書かれた刀剣世界を、作品に切り込みながら紹介しています。
町医者の娘が辻斬り事件に挑む「かまいたち」
作者の宮部みゆき氏は、ミステリー作家でもあり、同時に時代小説家としても精力的に活躍中。
東京都江東区深川で生まれ育ち、幼い頃から落語や講談、時代劇のドラマを楽しみ、それらの原作となった歴史小説・時代小説に親しみました。
1988年(昭和63年)には、短編集「かまいたち」が第12回歴史文学賞の佳作に入選。
表題作のかまいたちは、江戸幕府8代将軍「徳川吉宗」の時代を舞台として、夜な夜な江戸市中に出没しては人々を脅かす辻斬り・かまいたちの事件に、町医者の娘「およう」が挑むサスペンスです。

徳川吉宗
ちなみに、辻斬りに名付けられたかまいたちとは、つむじ風に乗って現れる3匹の妖怪のことで、1匹目が人を押し倒し、2匹目が鋭い鎌で切り付け、3匹目が血止めの薬を塗っていくと言われています。
しかも人の目には見えないため、つむじ風で転倒したその人は、切り傷を負ったにもかかわらず血が出ていないという不思議な現象に見舞われるのです。
刀剣小説の解説では、この宮部みゆき氏についても、生まれ故郷である深川と作品との深いつながりに触れ、作品に登場する妖しくも人情味を感じさせる刀剣の描写に言及しています。
大正・昭和生まれの刀剣小説家
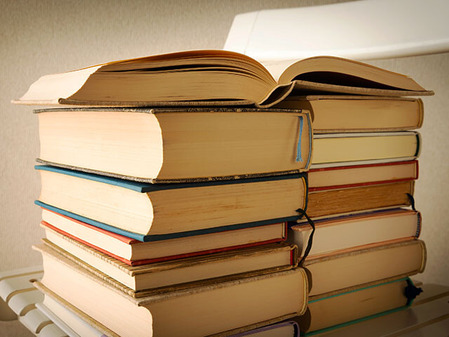
大正・昭和生まれの刀剣小説家は、大正時代から昭和の戦前までに生まれた刀剣小説家を紹介している項目です。
この時代以前には、刀剣小説の題材としてあまり注目されていな
かった忍者や隠密、剣客(けんかく:剣術に優れた人)が取り上げられるようになったことなどに触れています。
掲載されている有名な作家の中から、「山田風太郎」(やまだ
ふうたろう)氏をご紹介しましょう。
剣豪が妖術でよみがえる「魔界転生」
「忍法帖」シリーズで知られる山田風太郎氏は、卓越した想像力をもって忍法を描き、手に汗握る展開で読者を魅了。
そして、将軍家の兵法指南を務めた剣豪「柳生十兵衛」(やぎゅうじゅうべえ)を通して、刀剣の魅力を描き出しました。
1981年(昭和56年)に実写映画化もされた「魔界転生」
(まかいてんしょう)では、江戸幕府3代将軍「徳川家光」の時代に、幕府転覆をもくろむ「由比正雪」(ゆいしょうせつ)が妖術師に命じて、この世に未練を残す7人の剣豪をよみがえらせます。
この由比正雪のたくらみを阻止するべく立ち向かうのが柳生十兵衛であり、よみがえった剣豪のひとり、宮本武蔵(みやもとむさし)との対決がクライマックスです。
刀剣小説では、魔界転生に登場する宮本武蔵が、「吉川英治」
(よしかわえいじ)氏の長編「宮本武蔵」へのオマージュとなっていることなど、作品の一部を抜粋しながら解説しています。
明治30~40年代生まれの刀剣小説家
明治30~40年代生まれの刀剣小説家の項目では、映画が映像娯楽の主流であった時代からテレビの時代となる移行期に活躍しました。
作品の多くがNHKの大河ドラマとなったことで、現代の人々が抱く時代劇や刀剣のイメージに大きな影響を与えています。
この項目でも数多くの作家を掲載。その中から、「海音寺潮五郎」(かいおんじちょうごろう)氏に注目しました。
「天と地と」で描かれた上杉謙信のリアルな姿
海音寺潮五郎氏が作品を執筆する上で、重視していたのがリアリズム。史伝に重きを置いたノンフィクションを目指し、武将の生き様を巧みな筆致で表現しています。
「天と地と」では、越後国(現在の新潟県)の戦国大名「上杉謙信」を主人公として、その出生から「第4次川中島の戦い」までを描きました。
また、「正親町天皇」(おおぎまちてんのう)から「粟田口吉光」(あわたぐちよしみつ)作の短刀「五虎退」(ごこたい)を拝領したことなど、上杉謙信にまつわる刀剣についても触れています。
これは、海音寺潮五郎氏が愛刀家であったことが大きく関係しており、刀剣小説では、海音寺潮五郎氏が手に入れた名刀について、あるいは刀剣に関する随筆や史伝を残したことにも言及。刀剣を愛した海音寺潮五郎氏の姿勢にも記述は及んでいます。
もちろん、主人公である上杉謙信が愛刀家であったことは言うまでもありません。さらに、上杉謙信の養子で家督を継いだ「上杉景勝」(うえすぎかげかつ)も刀剣を愛し、上杉家に伝わる刀剣の中から特に優れた35振を選び、「上杉家御手選三十五腰」
(うえすぎけおてえらびさんじゅうごよう)に記しました。
この五虎退の他、「刀剣ワールド財団」が所蔵する「太刀 国宗」も、その内の1振です。
制作者の「国宗」(くにむね)は、鎌倉時代中期の備前国長船出身。のちに鎌倉へ移住し、鎌倉時代を代表する名工「新藤五国光」(しんとうごくにみつ)に技法を伝授したことでも有名です。

太刀 国宗
明治20年代生まれの刀剣小説家
明治20年代生まれの刀剣小説家が活躍した時代は、サイレント映画(無声映画)からトーキー(発声映画)への移行期にあたり、役を演じる俳優の声を聴くことができるようになりました。
数々の刀剣小説が映画化され、小説の主役と俳優のイメージとが重ね合わされることとなったのです。
刀剣小説に掲載されている作家の中から、「直木三十五」(なおきさんじゅうご)氏をピックアップ。直木三十五氏の名前は、「直木賞」として現在も広く知られています。
「由比根元大殺記」の他にはない立ち回り表現
刀剣をこよなく愛していたと言われる直木三十五氏は、刀剣や剣豪に関する評論や記述を数多く残しました。その心の奥底には、常に剣士への憧れがあったと伝えられています。
刀剣小説家としての直木三十五氏の代表作である「由比根元大殺記」(ゆいこんげんだいさつき)では、江戸時代初期の徳川家光と、弟である「徳川忠長」(とくがわただなが)との次期将軍の地位を巡る兄弟対立を描きました。
主人公は、徳川忠長に仕えることになった京流の剣客「牟禮郷之助」(むれごうのすけ)です。牟禮郷之助は、徳川家光と、その乳母「春日局」(かすがのつぼね)と敵対することになります。
刀剣小説では、牟禮郷之助が見せる立ち回りの描写がきわめて独特であることに言及し、小説本文の一部を抜き出して掲載。
直木三十五氏が、ありふれた立ち回りとは趣を異にする表現を目指したことを紹介しています。
明治元年~10年代生まれの刀剣小説家
映画・ドラマでも人気を博した「銭形平次捕物控」
もとは空想科学小説(SF)「二万年前」を執筆していた野村胡堂氏でしたが、当時人気の高かった「岡本綺堂」(おかもときどう)氏の「半七捕物帳」(はんしちとりものちょう)のような作品を書いてほしいと依頼され、「銭形平次捕物控」(ぜにがたへいじとりものひかえ)を執筆します。
銭形平次捕物控の舞台は、江戸幕府8代将軍・徳川吉宗の時代。主人公の銭形平次は江戸の岡っ引きです。投げ銭(寛永通宝[かんえいつうほう]:4文銭)の得意技を持ち、事件を解決に導きます。
この投げ銭は中国の小説「水滸伝」(すいこでん)に登場する張清(ちょうせい)が得意とした、「石つぶて」から着想を得たと言うことです。
銭形平次捕物控は、連載が始まって間もなく映画化され、その後のテレビドラマでも人気を博しました。
野村胡堂氏は「新刀」よりも「古刀」を重視したと言われ、作品には「正宗」や粟田口吉光、「郷義弘」(ごうよしひろ:江義弘)、「貞宗」(さだむね)ら高名な刀工の刀剣が登場。刀剣小説では、刀剣に対する野村胡堂氏の創作姿勢にも触れています。
読み物としても楽しめる刀剣小説ページ
刀剣小説・歴史小説選びの指針として役に立つ、刀剣小説紹介ページ。総勢45名以上の著名な作家が詳しく解説され、読むだけでも大いに楽しめるコンテンツとなっています。
刀剣小説・歴史小説は、歴史書や解説文とは違い、別の角度から刀剣の魅力に迫ることができるのもポイントなのです。
また、小説の世界に浸って物語を堪能したのちに、名古屋刀剣博物館「名古屋刀剣ワールド」へ足を運んで、本物の刀剣に出会ってみてはいかがでしょうか。