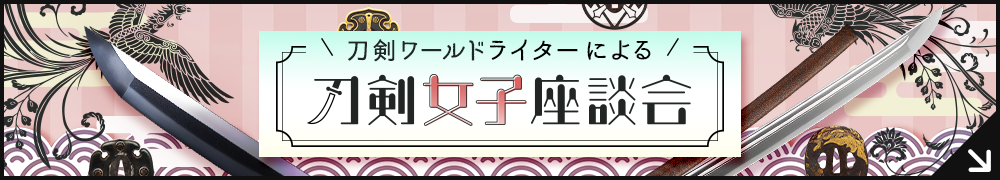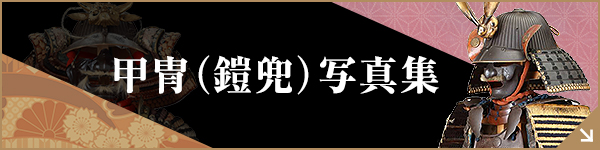甲冑の歴史と変遷 - 刀剣ワールド
- 小
- 中
- 大

刀剣ワールドライターの青虫です。
合戦には欠かせない、体を守るための防具である日本の甲冑の魅力と言えば、威風堂々の立ち姿や武士の精神などが垣間見える、ロマンに溢れているところ!そんな甲冑の歴史は、古くは古墳時代にまでさかのぼることができるのです。中国から伝来した甲冑は、日本の古代王朝の成立と共に発展し、高い芸術性のある、日本独自の甲冑に進化していきました。時代と共に変化する甲冑の歴史について見ていきましょう!
武家が勃興した平安時代から鎌倉時代の甲冑
平安時代の騎射戦に特化した大鎧
一般兵士の防具から上級武士の防具へと進化した胴丸

胴丸の部位
胴丸は元々、徒歩戦(かちせん)を行う騎乗しない一般兵士が用いた防具で、足さばきが良く、右脇で胴を引き合わせて着用するのが特徴の甲冑です。
大鎧とは違い、基本的に胴丸は単品で使用され、兜や袖などを付けないのが一般的。その代わり、肩上(わだかみ:甲冑の肩部分)に「杏葉」(ぎょうよう)という手のひら大の鉄板を下げて、肩上を防護したのです。
集団戦で大鎧よりも機敏に動ける胴丸は、鎌倉時代後期以降も着用され続け、大鎧が実戦で用いられなくなると、上級武士の間で兜と袖を揃えた胴丸が着用されるようになりました。
また、平安時代には上級武士の大鎧と機敏性を重視した胴丸が合わさった形式の「胴丸鎧」が制作されます。
現存する胴丸鎧は1領しかなく、しかもその1領は、「源平合戦」の英雄「源義経」が奉納したことで有名な超レアな甲冑。「大山祇神社」(愛媛県今治市)に所蔵されており、他にも「源頼朝」が奉納した甲冑も一緒に鑑賞することができるので、源氏好きの方はぜひチェックしてみて下さい!
集団戦に特化した南北朝時代から室町時代の甲冑
より簡易的で機動力に優れる腹巻の流行
南北朝時代から室町時代にかけての甲冑のスタイル
南北朝時代になると合戦はより激しいものとなったため、兜や袖の他にも、頬当や喉輪、籠手、臑当、佩楯などを完備し、全身を隙間なく包む甲冑へと変化していきます。甲冑の需要も増えたため、甲冑の素材も簡略化された物が流行しました。
また、甲冑の中でも特に目を引く兜の前立が流行しはじめたのも南北朝時代頃だと言われています。
本来、前立の「鍬形」(くわがた)は、大将の威厳などを示すために用いられた物。ですが、当時流行した「ばさら」と呼ばれる身分秩序を無視し、派手な振る舞い、粋を好む美意識が甲冑のスタイルにも反映され、多くの武将達の兜にも前立が付けられるようになりました。
前立の形も多様化し、強さを象徴する「獣角」や、生命を象徴する「日輪」、不死と再生を意味する「月輪」(がちりん)などが当時の流行。甲冑のスタイルは、当時の武将達の美意識、つまり、おしゃれが牽引していたと言えるのです。
個性が光る!戦国時代から安土・桃山時代の甲冑
今風の甲冑と呼ばれた当世具足
当世具足は、「防護機能を完備した現代風の甲冑」という意味を持ち、全国的に広まった乱世を生き抜く知恵を結集させた甲冑です。
当世具足には決まった形がなく、武将達が合戦で得た経験をもとに制作や改良がされました。武将達は城下にお抱えの甲冑師を雇い、特注の甲冑を制作させたことで、全国にそれぞれの特色が強い甲冑が誕生していったのです。
なお、当世具足は甲冑の形状だけでなく、装飾にも武将達の個性が光りました。甲冑は本来、身を守るための防具ですが、命のやり取りをする戦場においては「ハレの場で着用する衣装」や「死に装束」という意味も持ち合わせています。
そのため、甲冑には、信仰する神仏や勇ましさを表す動物などの様々な意匠を用いて、信念や威厳、祈りなどの精神的な意味を込めたのです。
変わり兜の登場
安土桃山時代には、「何コレ!?」となるような風変わりな兜が流行。元々は、信念や威厳を表していた前立が兜の脇や後ろにも付けられるようになり、さらには動物の毛などを用いて、兜に奇抜な装飾が施されるようになったのです。

黒田長政所用の甲冑
これらの装飾が兜と一体化した物が「変わり兜」と呼ばれる兜。源平合戦の古戦場である「一の谷」の地景を模した「黒田長政」所用の兜や、兜の天辺が2つに裂けた形の、「蒲生氏郷」(がもううじさと)所用の
「鯰尾兜」(なまずおかぶと)などが有名です。
変わり兜は、一目見ると個人の特定もできるため、勇猛さを相手に知らしめたり威嚇したりする意図も含まれた、まさに血で血を洗う「戦国スタイル」の象徴とも言えます。
戦のなくなった江戸時代の甲冑
復古調の甲冑が流行

復古調の大鎧
江戸時代には、町人文化の影響や、実戦が行われないこと、武士の身分が固定されるなどの理由により、甲冑は実戦的な物ではなく、家柄を表す表道具として華美な装飾が施された物が流行。
さらに、江戸時代中期頃の復古主義的な風潮も後押しし、大鎧などのきらびやかで古風な甲冑が盛んに制作されることになったのです。
しかし、正しい古式の甲冑の形式が理解されないまま制作されたことも多かったため、本来胴丸に附属しない栴檀板や鳩尾板が付けられるなど、オリジナリティーの溢れる甲冑が制作されることも少なくありませんでした。
一方、各藩には甲冑師が抱えられ、戦国時代より続く技術を継承していく「御家流」の甲冑が登場。
「伊達政宗」が初代藩主となった仙台藩などでは、伊達政宗が好んで着用した「雪の下胴」と呼ばれる胴の形式が幕末まで変わることなく継承され、藩主から足軽まで着用され続けたのです。
装飾品となった現代甲冑
幕末の動乱期以降、銃をはじめとする火器の著しい進歩により、防具としての機能を果たせなくなった日本式甲冑の意義は、美術品としての意味合いがより一層強くなりました。
日本刀と同様に、武士の精神性を表してきた甲冑は、男子の健やかな成長を祈る「五月人形」をはじめ、現代日本でも強さや勇敢さを表す物として扱われているのです。
受け継がれる武士の精神
現代の甲冑と言って真っ先に思い浮かぶのが、端午の節句で飾られる甲冑です。男子の健やかな成長を祈る際に飾る物として、有名武将が着用したモデルの甲冑は大変な人気があります。
今では、たくさんの伝統技術が詰まった日本式甲冑に防具としての機能はありませんが、武士が甲冑に込めた信仰や信念、勇猛さの象徴としての意味合いはなくなることはありませんでした。
現在、甲冑は端午の節句に飾ること以外に、多くのレプリカなどが制作され、鑑賞するだけでなく、博物館のイベントや一部のフォトスタジオなどで着用することができます。
甲冑を着て、当時の武士の気持ちを体験したい!という方は、インターネットなどで調べてみるのがおすすめ。戦国ロマンが溢れる威風堂々たる姿に変身することができますよ!